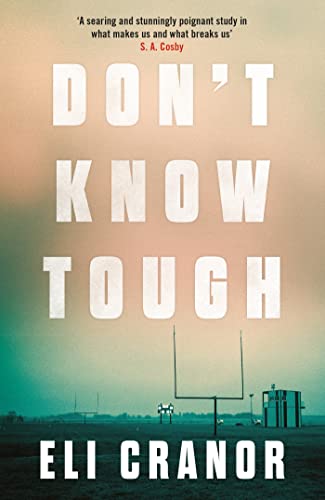さて、今回は『Don't Know Tough』by イーライ・クレイナー徹底解説と題しまして本書を徹底的に語りたいと思います。
とにかく凄かった……。まさにハードブロウを食らったかのような衝撃を受け、しばらく頭の整理がつきませんでした。あらすじをまとめようとして読み返すとまた新たな気づきがあったり、それまでの自分の解釈は正しかったのだろうかと疑問を持ったりで、反芻にこれまた時間がかかりました。文章自体は読み易くストレートに頭に入ってきますし、ページ数も323ページと、それほど長くもありません。一応ノワール物として2023年度エドガー賞新人賞にもノミネートされていますが、もはやジャンルを越えた文学作品と言えるのではないでしょうか。ヘミングウェイ級の力強くストレートな文体、そして『エデンの東』を彷彿とさせるスタインベックばりのドラマ性。いやいや、凄まじいインパクトがある作品でした。
【あらすじ】
アーカンソー州イザード郡デントン。そこはマクドナルドも一店しかない田舎町。デントン高校のフットボール・チームのプレーオフ進出はビリー・ロウ選手の肩にかかっていた。彼は気性が激しく、ときに自制がきかなくなるが、才能に溢れるランニングバックだ。育った家庭は荒れていた。トレーラー・ハウス住まいで、シングルマザーの母親の恋人に酷い虐待を受けてきた。その男への怒りをフィールドで発散させている。火の玉のような彼を止めることができる選手はいない。
しかしある日、練習中にチームメイトに対してラフプレーをやり過ぎてしまい、謹慎処分を受ける。次の試合の出場停止という苦渋の決断を下さなければならなくなったのは、カリフォルニアからやってきたばかりの新監督トレントだった。トレントは校長や古顔のコーチから圧力を受けながらもなんとかビリーが試合に出場できる道を探る。トレント自身も辛い幼少時代を過ごしてきたが、フットボール・チームの監督に拾われ、洗礼を受けてクリスチャンとなり、以来生まれ変わった人間となって今の地位を築いたからだ。
そんなときビリーの母親の恋人がトレーラー・ハウスのなかで死んでいるのが発見され、ビリーが疑われる。ビリーを救うことが神からの使命だと考えるトレントは彼を守ろうとするが、悪い事態はさらに悪い事態を引きよせ、負の連鎖は止まらなくなっていく。そして運命の試合の日は刻一刻と近づいてくる――。
田舎町特有の狭い人間関係
舞台はアーカンソー州イザード郡のデントン。小さな田舎町というだけあって出てくる人物たちの密な相関関係にこっちの息まで詰まりそうになってきます。
例えば主人公のビリーには兄のジェシィがいて、彼も昔は高校のフットボール・チームのクォーターバックでした。今はラクリーシャという女性と別のトレーラー・ハウスで同棲中でネシーという赤ん坊もいます。ラクリーシャはビリーの元カノで、赤ん坊の父親はビリーだと公言。彼女の兄のローマは、ビリーのせいで妹は高校中退を余儀なくされたと思い、ビリーを恨んでいます。(この恨みがのちの悲劇を生み出す要因のひとつとなるのですが)。
しかしビリーは、赤ん坊の父親はジェシィだと本能的に確信しています。そこからは、兄が弟の恋人を寝取ったことが容易に推測できます。そもそもビリー一家とラクリーシャ一家は同じトレーラー・パークで育った幼なじみでした。ラクリーシャの兄のローマはジェシィの元チームメイトでポジションはストロングセーフティ。現在は保安官補になっています。ちなみに保安官のティモンズも元チームメイトでポジションはラインバッカーでした。そのチームで監督を務めていたのが、今は校長となっているブラッドショー、といった具合です。
貧困、人種差別、そしてフットボール――それは合法麻薬のレシピ
本書に政治色はありませんが、アメリカの南部に根深く存在する”暗部”を鋭くえぐるクレイナーさんの筆致からある種の政治的側面を窺い知ることができます。この町の産業は養鶏だけ。町に入れば生ぐさい臭いが鼻につく。大半の住民は鶏肉の精肉工場で働いているという典型的なホワイトトラッシュの地にあって、高校のアメフトチームの活躍は唯一の娯楽となっています。試合は町民のプライドを賭けた最大のショーであり、勝利には麻薬のような作用があります。人々は勝利に自分たちを重ね合わせて優越感に浸る。そこにあるのは、勝者は敗者より強い、という純然たる事実と、それが引き起こす恍惚感です。クレイナーさんはこれを、”副作用のないドラッグ”と表現しています。
さらに、そこへ人種差別という意識が加わります。多様性だのポリコレだのはどこ吹く風とばかりに、校長は断言します。一滴でも非白人の血が混じっていたらおまえは黒人なのだ、と。カリフォルニアからやってきた新任監督のトレントは、生まれがミシシッピだというだけで校長に、先祖に黒人の血が混ざっているのではないかと疑われます。それが南部の考え方なのです。古参のコーチであるブルも、”ここはデントンだ。世間の常識は通用しない。町には町のルールがある”とトレントにアドバイス。この白人至上主義と、スポーツの勝利から得られる優越感。レッドネック、あるいはホワイトトラッシュと呼ばれる彼らのアイデンティティーの拠り所はそこしかないという現実。このあたりからは、”アメリカ・ファースト”を連呼するトランプ前大統領がなぜ支持されているかが透けて見えるような気がします。
主人公ビリーの魅力
本書に登場するキャラクターは誰もがリアリティーに溢れていますが、中でも主人公のビリーは圧倒的な存在感を放っています。幼いころから母親の恋人のトラヴィスに虐待されてきたビリー。とはいえ殴る蹴るの暴力を受けてきたわけではありません。彼が受けてきたのは根性焼き――火のついた煙草を皮膚に押しあてられる行為です。冒頭、ストーリーはこの根性焼きにビリーが必死で耐えているところから始まります。泣いたり騒いだりしてトラヴィスを楽しませたくない、そんな一心で、吸いさしを押し付けられてもなんでもないことであるかのように平静を装うのです。そうやって痛みや感情を殺すことを学ばざるをえなかったビリー。フィールドは鬱積した怒りを爆発させる唯一の場所でした。フィールドでの彼はまさに闘犬。彼を止めることができるほどの選手はどこを探してもいない。
さらに彼はボールを持ったら絶対にファンブルしない。それは、普段母とトラヴィスの間にできた赤ん坊を抱っこしているから。万が一赤ん坊を落としてしまったら大変なことになります。アメフトと関連づけた、弟への愛情と責任感の描写はさすが! 彼の優しい心根が感じられる瞬間です。しかし、大切にされる、ということを知らずに育ったビリーには共感力が欠如していました。プレーオフ戦でタッチダウンを決めたビリーにハイタッチをしようとする監督のトレントをビリーは無視。監督は、「ハイタッチはなしか?」と訊きます。(このシーン、原文ではハイタッチが”love”になっています。つまり直訳すると、愛はなしか?と訊いているんですね)ですがビリーには喜びを共有するということがわからない。試合後には相手選手と握手をしろと言われてもまた無視。握手や、ハグまでしている選手たちを不思議そうに眺めます。結局、彼は皆に自分勝手なやつと思われ、勝利の立役者なのに誰からも関心を払われません。こんなに点数入れているのにどうしてなんだ――とビリーは孤独を深めていきます。そんな折り、監督の娘のローナからヘミングウェイの『老人と海』を勧められ、それまで本など読んだことのなかった彼が一生懸命読むようになるのです。ローナがそれを勧めたのは、ビリーが奨学金を得て大学に進学できるようにするためでした。周りからの支えを得て彼の固く閉ざされていた心が少しずつ開いていくと、その内側にある無垢な少年らしさが見え隠れしてきます。しかし、せっかく前向きになりかけたビリーを再び負の引力が……。
信仰は負の連鎖を生みだすのか、それとも断ち切るのか
本書のもう一人の主人公と言えるのが新任監督のトレントです。彼自身も里親をたらい回しにされた少年時代を過ごしてきた経験があるため、ビリーを自分に重ね合わせてなんとか救おうとします。トレントの場合は十五歳のときにアメフトの監督のドマーズに見いだされ、養子にしてもらって洗礼を受けてクリスチャンになってから人生が変わりました。クォーターバックの選手として活躍したあとはドマーズの後押しを受けて母校の監督に。しかし負け続きで解任され、起死回生をかけてデントンにやってきたのです。ですが勝つことだけを目標とはしていません。フットボールを通じてよりよい夫、父親、よりよい人間になることを学んでほしいと思っています。そしてビリーのような少年を救うことが神から与えられた使命だとも。
とはいえその信念に基づいた彼の行動には賛否が分かれることでしょう。
『老人と海』との関連性
クライマックスのエピソードは”エデンの滝”という、実在する洞窟で繰り広げられます。(ユーチューブで見たのですが、やはり見てから読むとより臨場感が感じられますね)そして、ある意味非情とも言えるエンディング。確かに負の連鎖、不幸の顛末と言ってしまえばそれまででしょう。しかし本当に希望はないのでしょうか。何度読み返しても確信は得られません。でも私は、トレントは殉教者であり、ビリーに確実に大切なことを伝えたのではないかいう解釈に達しました。本書と『老人と海』との関連性を見いだせたからです。
『老人と海』は、おおざっぱにあらすじを説明しますと、キューバに住む一人の老漁師と彼を慕う少年がいましたが、ある日老人は海に出て巨大なカジキを3日間にわたる死闘の末に捕獲します。しかしその後にサメに襲われてカジキを食い尽くされ、骨だけを持って港に帰ってくるという話です。この物語には以下のような考察が散見されました。
老人にとって敗北は敗北でない。彼は物事を結果で判断しない。魚との闘いを通して、自己の力や勇気、人間としての犯しがたい尊厳を保とうとしている。老人の魚やサメとの闘いは、与えられた機会にいかに全力を出しきれるかにある。
カジキの捕獲は、老人が漁師としての名誉をとりもどすチャンスだった。しかし、捕まえたカジキは港に戻る途中で失ってしまう。それは人生の残酷さを象徴しているかのよう。老人はすべてを失ってしまったが、少年に技術と希望を伝えることができた。
下の世代に価値あることを伝えられたことによって、老人の人生も報われたのかもしれない
これらはまさにトレントとビリーの関係を象徴しているように思えてなりません。トレントは再起を賭けてデントンにやってきて、そこでビリーという天才選手に出会い、チャンピオンシップへの進出も実現しかけたところで、ビリーはサメのような大人たちに食いちぎられ、トレントは監督としての名誉を挽回することはできなくなります。しかし老人が少年に希望を伝えられたように、トレントが自らを犠牲にしてまで伝えたかったことはしっかりとビリーに受け継がれていると思いたい。そこに、負の連鎖が断ち切られる希望を私は見いだしましが、読者の皆様はどうお感じになるでしょうか。いずれ邦訳されるでしょうから、そのときにはぜひ皆様のご意見をお聞きしてみたいと思います。
さて、イーライ・クレイナーさんの新作『Ozark Dogs』はデビュー作である本書を超えたと大評判です。
勿論読むつもりではありますが、少し時間を置きたいというのが正直なところ。平易な文章で読みやすいのですが、行間から伝わる熱量がハンパじゃない。メンタルが持っていかれてしまいます。現に『Don't Know Tough』を読んでから二週間たっているのにまだ呆けている私がここにいいます。
いやはや、凄い新人が出てきたものです。十年、いや五十年に一人の作家と言ってもいいのではないでしょうか。